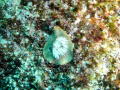2016年8月13・14日 MIKOMOTO3 神子元ハンマーズ、OSEZAKI2 大瀬館マリンサービス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
6 |
ヒロウミウシ |
ピンク色の小さなウミウシです。緋色ウミウシかと思いきや、ヒロウミウシでした。
緋色でなければ、小さいのに何で”広”なのでしょうか? よく調べたら、学名が「Okenia hiroi」でした。 |
(大瀬崎 先端) |
7 |
セスジミノウミウシ |
これも小さなウミウシです。ミノウミウシの仲間ですが、セスジというのは、かすかに
見える青い線のことのようですね。 カメラが良くてストロボがあれば、もっと綺麗な色だったのですが・・・。 |
(大瀬崎
オスパー前) |
8 |
ウデフリツノザヤウミウシ |
通称「ピカチューウミウシ」ですね。
これも、もっと綺麗な色なのですが・・・。 交尾でしょうか?ランデブー(古い?)状態でした。 |
(同上) |
9 |
スナイソギンチャク |
綺麗な黄色のイソギンチャクです。名前の通り、砂地にいました。
真ん中のヘリポートのようなマークは口ですね。 |
(大瀬崎 先端) |
10 |
ナシジイソギンチャク |
ウミウシかヒラムシか・・・???
ヒラムシにしては鰓のようなものがあるし、ウミウシにしては触角がないし・・・・。 いろいろ悩んだのですが、鰓のようなものの数が多いので、イソギンチャクの若者では? と考えました。自分の検索では判らず、Facebookの「44の海の談話室」に相談した所、 普段はヤギに着いている個体がホストの死滅などで流され、次のヤギに巡り合えずに とりあえず地面にへばりついているのでは、とのお答えでした。確かにそんな感じですね。 ちなみに、「ナシジ」とは、梨のような地模様という意味だそうです。これも納得! |
(神子元 カド根) |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
11 |
アオサハギ(幼) |
日本の海であまり潜らないので、こんな魚がいるとは知りませんでした。
名前の通りアオサの陰にひっそり佇んでいました。 大きさは2〜3cm、大人になっても数センチだそうです。 |
(大瀬崎
オスパー前) |
12 |
ホシノハゼ |
ハゼもたくさんの種類がいますが、これは、目の周辺が黒いのが特徴だそうです。
青飛びしているので白っぽく見えますが、実際はもう少しオレンジ〜茶系です。 |
(大瀬崎 先端) |
13 |
コウライトラギス |
トラギス属にも何種類かありますが、他の種類の多い魚にもコウライという名前が付いた
ものがあります。高麗は朝鮮半島の昔の国名ですが、似て非なるものでちょっと派手な ものにはコウライという名前を付けたのでしょうか? ちなみに本家トラギスも、朝鮮半島にもいるようです。 |
(同上) |
14 |
クサフグ |
ビーチへのエグジットの途中の浅場で見かけたので上からの写真になってしまいました。
背中が緑色っぽいので「草」の名前が付いたのだそうです。 子供のころに行った海水浴でもよく見かけた身近なフグですね。 |
(大瀬崎
オスパー前) |
15 |
ミジンベニハゼ |
大瀬崎に来たら見たいと思っていた魚ですが、ライティングが悪く、色もピントもよくない
です。ビンから出てきてくれたのですが、そのカットはもっとひどいのでこっちにしました。 次回行くときは、もっといい装備で臨みたいですね。 |
(同上) |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
16 |
オオスジイシモチ |
前回の大瀬崎ではコスジイシモチを撮りましたが、今回は「大筋」です。
比べると確かに筋の太さが違います。また、筋が太い分本数も5本と少ないですね。 目玉の二本線は同じですが、こっちのほうがなぜか傾いています。 |
(大瀬崎 先端) |
17 |
オトメニシキ? |
(同上) |
|
18 |
トラフカラッパ |
これもライトが届かず青飛びしていますが、実際はもう少し赤茶色ですね。
トラフというのは虎の模様という意味だと分かりますが、カラッパって?調べてみたら、 インドネシア語でヤシの実をkelapaといい、ヤシの実のようなカニということのようです。 |
(大瀬崎
オスパー前) |
19 |
ウスユキミノガイ |
ウコンハネガイと同じミノガイ科の貝ですね。
ウコンハネガイは怪しく光りますが、こちらは薄絹のようなセクシーな半透明の色使い です。深場の岩の隙間のウコンハネガイと違い、浅い砂地にいるそうです。 |
(大瀬崎 先端) |
20 |
ホシササノハベラ |
元々は、アカササノハベラと同じ種類と思われていたそうで、海中でも同じ種類に見え
ました。なので、アカササノハベラの写真が撮れたので、こっちは真剣に撮りません でした。なので、こんなピンボケの写真しかありませんでした・・・。(^^;; 違いは、目の下 の線が胸鰭まで曲がっているのが「アカ」、真っ直ぐなのが「ホシ」だそうです。 |
(同上) |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
21 |
イイジマフクロウニ |
イイジマというのは、東大の教授の名前だそうです。
とげには神経毒があり、声が出なくなるほど強烈だそうです! メロンパンのチョコレート版みたいで美味しそうですが・・・、くわばらくわばら。 |
(大瀬崎 先端) |
22 |
イトフエフキ |
(同上) |
|
23 |
アカオビハナダイ(オス) |
ライトの当たる距離でバッチリ鰭を広げてくれました!シミランでも載せていますが、
鰭の先の藤色まで綺麗に撮れたので再度載せました。背景がゴロタでちょっと何ですが。 36mとちょっと深場ですが、綺麗なハナダイがたくさん群れていました。 |
(同上) |
24 |
メジナ |
神子元では、結露の犠牲になりボケボケの群れの写真が載っていますが、今回やっと
図鑑らしいのが撮れました。鼻の孔と分厚い唇が特徴的ですね。 |
(大瀬崎
オスパー前) |
25 |
ミギマキ |
最初の八丈島でぐるぐる右に回る写真を載せていましたが、今回は図鑑的なのを撮りま
した。名前の由来は、身際巻きが訛ったとか、タカノハダイをヒダリマキというからだとか の説があるそうです。体の黄色と黒に対し、口と鰓のオレンジ色が生々しいですね。 |
(神子元 カド根) |
26 |
27 |
28 |
29 |
26 |
オキゴンベ |
(大瀬崎
オスパー前) |
|
27 |
トラフナマコ |
今回はフィルターなしカメラなので、どれも発色が悪いのですが、これも本来ならベージュ
に茶色の斑(フ)が入っているのですが、黒いシミにしか見えませんね。 TG-4でもう一度リベンジしたいです。 |
(同上) |
28 |
イサキ&タカベ |
ここからはGoproのムービーです。
今年の神子元ではハンマーは見れませんでしたが、イサキとタカベの群れはいつも楽しま せてくれます。どの群れも、終わったと思ったら突然また沢山現れるのが楽しいですね。 |
(神子元 カド根) |
29 |
イサキ(幼) |
大瀬崎ではイサキの幼魚の大群がプランクトンを食べていましたが、そこにカンパチの
子供が捕食に突っ込んできて右へ左へ大騒動・・・! |
(大瀬崎 先端) |
30 |
ソラスズメダイ&
イシダイ(幼) |
水深1m余りのエグジット前のところです。たくさんのソラスズメダイが舞っているところに
イシダイの子供たちが乱入してきました。 涼しげなムービーになりました。 |
(同上) |